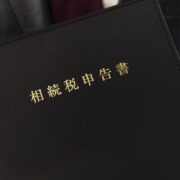家の庭にごみを放置したり埋めたりするのは違法?罰則や対処法まで解説
生活するにあたってごみ出しを忘れた、ごみが溜まってごみ箱にはいらない、といったケースはよくあることです。ごみの処分に困ったとき「所有地だから放置しよう」「自分の土地に埋めてもわからないだろう」と考える人もいるようです。
しかし、このようなケースは法律に違反している可能性があるため、注意しなければなりません。
本記事では家の庭にごみを放置したり埋めたりするのは違法なのか、罰則はあるのかどうかなどについて解説します。
【結論】

自分の所有地であっても、庭にごみを放置したり埋めたりする行為は、原則として「廃棄物処理法」違反(投棄禁止)に当たり得ます。 同法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
※過去には規模要件が議論された時期がありますが、現在は原則として許可された処分場以外での埋立ては不法投棄と解され、自社(自宅)敷地内でも違法となり得ます。
廃棄物処理法とは
正式名称は**「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」。目的は、廃棄物の適正処理を通じて生活環境の保全と公衆衛生の向上**を図ることです。投棄禁止(16条)などの基本規定が置かれています。
| この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 |
引用:e-Gov「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
つまり、廃棄物処理法はごみの適正な処理を目的としており、ごみの放置や埋め立てといった公衆衛生の低下を防ぐために設けられた法律です。
所有地にごみを放置・埋め立てしたときの罰則
所有地にごみを放置・埋め立てした場合、廃棄物処理法の以下の内容に違反します。
| 廃棄物を埋めたり放置したりする行為は、自分の土地、他人の土地にかかわらず、廃棄物処理法第 16 条の投棄禁止に違反する「不法投棄」にあたります。 |
引用:大阪府「産業廃棄物による土地造成等の禁止」
廃棄物処理法第16条には「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。
そして、違反すると以下のような罰則を受けるケースがあります。
| 個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方
法人の場合は3億円以下の罰金(廃棄物処理法第25条及び32条) |
| 3年以下の懲役刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方(廃棄物処理法第26条) |
引用:e-Gov「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
このように廃棄物処理法に違反すると、高額な罰金や懲役刑が科されます。
自分の所有地でも対象となるため、放置や埋め立てはしないよう適正に処理しましょう。
ごみを放置・埋め立てしたときに起こる問題

ごみを放置・埋め立てすると、近隣からの苦情や訴訟に発展するおそれがあります。
生ごみなど臭いを発するものを放置すれば、悪臭で迷惑をかけることになり、ひどい場合は損害賠償を求められる可能性もあります。
また、家電や家具など大きなごみを積み上げると崩れて危険です。
もし崩れたごみで通行人にケガをさせた場合、廃棄物処理法違反に加えて損害賠償の対象にもなります。
「少しだけなら大丈夫」と考えていると、大きなトラブルを招く可能性があることを覚えておきましょう。
実際に起きた裁判事例
個人が自宅の敷地にごみを放置・埋め立てして裁判になった事例は少ないですが、法人による違反事例はいくつもあります。
たとえば、「野積み不法投棄事件」(最高裁平成18年2月20日判決)では、
アルミ精錬工場が産業廃棄物約1トンを工場内の穴に埋める予定で3か月間積み上げていたところ、
裁判所は「仮置きではなく、廃棄行為にあたる」と判断しました。
つまり、自分の敷地内でも管理がされていなければ“捨てた”とみなされるということです。
結果、被告の上告は棄却され、廃棄物処理法違反が確定しました。
個人の場合、摘発されにくいだけで、違法行為であることには変わりません。
見つかれば同様に処罰される可能性があります。
ごみを適切に保管・処分する方法
ごみを放置・埋め立てしないようにするには、適切な保管方法や処分方法を理解する必要があります。
主なごみの保管方法・処分方法は、以下のとおりです。
- 生ごみを新聞で包み、袋を二重にする
- ごみ袋にキッチンペーパーを敷く
- 大きなごみは粗大ごみとして引き取ってもらう
- リサイクルショップを活用する
- 自治体で引き取れないものを知っておく
ごみの保管方法・処分方法を理解しておけば、放置したり埋め立てしたりしなくてもよくなるはずです。
生ごみを新聞で包み、袋を二重にする
生ごみを新聞で包み、袋を二重にしておけば、ニオイを和らげられます。
生ごみのニオイは、菌の繁殖によって起こります。
新聞紙に包んでおけば水分を吸い取ってくれるため、菌の繁殖速度を抑えることが可能です。ただ、菌が繁殖していなくてもニオイを発生させるごみもあるため、ごみをいったん袋に入れて縛り、その上からごみ袋を縛ってニオイを防ぐとよいでしょう。袋が二重になっていれば、ニオイが外に出る量を抑えられます。
しっかりとニオイ対策していれば、建物の外に置いたごみ箱に入れても近隣に迷惑をかけにくくなるはずです。もちろん、外に置くのは仮置きと認識し、次のごみ収集日には必ず出すよう心がけましょう。
ごみ袋にキッチンペーパーを敷く
大きなごみは粗大ごみとして引き取ってもらう
一定以上の大きさのごみを捨てる場合、特定の方法でないと引き取ってくれません。
たとえば、横浜市の場合、一番長い辺が30cm以上の金属製品、金属以外で50cm以上のものは粗大ごみに該当します。
そして、横浜市はインターネットから粗大ごみ回収の依頼、費用の決済が可能です。所定の手続きを終えたら、設定した収集日に引き取ってくれます。
なお、粗大ごみの引き取りには費用がかかる点に注意しましょう。
自治体によって金額が違い、引き取る粗大ごみの種類によっても異なります。
また、粗大ごみの引き取りの申込方法も異なるため、粗大ごみを処分する際には必ずお住まいの自治体に確認してから手続きしましょう。
リサイクルショップを活用する

ごみを捨てる前には、売却できないか検討することも大切です。
ごみを捨て処分するには、運搬や可燃など多くのエネルギーを消費します。ごみの量が増えるほどエネルギー消費量も増加するため、使えるものはそのまま残しておくとよいでしょう。
リサイクルショップに持ち込めば、他人が利用してエネルギー消費を抑えられます。価値のある物品なら、買取料を受け取れるのもメリットです。
自分にとって必要ない物品でも、他人が使ってくれそうだと判断したら、一度リユースできる方法がないか考えてみましょう。
自治体で引き取れないものを知っておく
ごみの多くは自治体が引き取ってくれますが、品目によっては引き取ってくれません。
横浜市の場合、以下の品目はごみとして収集してくれません。
- エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・パソコンといった一部家電製品
- 小型充電式電池・ボタン式電池
- バイク
- 消火器 など
自治体で収集しないごみを捨てる場合、それぞれの捨て方を理解しておく必要があります。
たとえば、小型充電式電池は一般社団法人JBRCが設置している黄色い回収缶に捨てる必要があります。どこに設置されているかはインターネットで調べられますが、まずは何を回収してくれないのか理解しておくことが大切です。
まとめ
ごみの処分に困ったとしても、所有地に放置したり埋め立てしたりすると廃棄物処理法に違反します。
廃棄物処理法では所有地かどうかは関係なく、ごみを適切に管理・処分していない行為が禁止されているからです。
個人が少量のごみを放置・埋め立てしても罰則を受ける可能性が低いといえますが、それでも違反しているという認識はもたなければなりません。もし近隣から苦情が出て訴訟に発展すると、高額な罰金や懲役刑を受けるおそれもあります。
廃棄物処理法に違反しないよう、適正に保管・処理していきましょう。

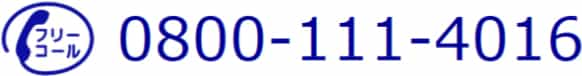
を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)