固定資産税を節税する方法があるって知ってますか?

小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、相続時に利用できる固定資産税の節税措置の一つです。この特例は、特定の条件を満たす住宅用地について、評価額を大幅に減額できるという制度です。相続税の計算基準となる土地の評価額が最大80%減額されるため、住宅を相続した際の税負担が大きく軽減されるメリットがあります。これは特に都心部や地価が高いエリアで大きな効果があらわれます。
節税例
例えば、都市部に300㎡の住宅用地を相続した場合、特例が適用されれば、評価額が80%減額されることになります。仮に土地の評価額が1億円だった場合、8000万円の減額となり、相続税の基礎となる額は2000万円に。これにより、相続税の大幅な削減が可能となります。
適用条件と制限
この特例を受けるためには、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります。例えば、以下のような条件が含まれます。
・被相続人が亡くなる直前まで住んでいた住宅であること。
・相続人がその住宅に住み続ける、もしくは貸家にしないこと。
・330㎡までの住宅用地が対象となる。※他利用区分によって適用条件が変わる
メリット
相続税の大幅な節約: 都市部で特に有効で、地価が高いエリアでの相続において大きな節税効果を発揮します。
長期的な財産保全: 自宅を相続する場合、この特例を利用することで、資産の現状維持がしやすく、財産を守る手段として有効です。
デメリット
適用条件が厳しい: 特例の適用には厳しい条件があり、特に相続人が住宅に住み続けることが求められる点が制約です。また、条件を満たさなければ特例が適用されず、結果として税負担が大きくなるリスクもあります。
適用範囲が限定的: この特例は相続時にしか適用できず、売買や贈与に対しては利用できません。さらに、土地の面積制限もあり、広大な土地には適用されにくい点がデメリットとなります。
新築住宅に対する軽減措置
軽減措置の内容と適用条件
新築住宅に対する軽減措置の内容は、主に固定資産税の評価額に対して一定期間、減額を行うものです。具体的には、居住用部分に対して120㎡以下の範囲で、新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)、固定資産税が半分に減額されます。また、この軽減措置は一戸建てだけでなく、マンションや共同住宅も対象となっています。
例えば、評価額が2,000万円の新築住宅の場合、通常の固定資産税は約30万円と計算されます。しかし、軽減措置を受けることで、1年あたり約15万円に減額され、3年間で45万円もの節税が可能です。

メリット
大幅な節税効果: 先述の通り、3年間で最大半額に減額されるため、新築購入時の税負担を軽減できるのは大きなメリットです。特に初期のローン返済が重く感じる時期に、この軽減措置が適用されることで、家計の負担を軽減することができます。
対象の広さ: この軽減措置は、戸建て住宅だけでなくマンションなどにも適用されるため、さまざまなタイプの新築住宅を購入する人にとっても有効です。
デメリット
軽減期間が限定的: この軽減措置はあくまで3年間(長期優良住宅で5年間)と期間が限られているため、その後は通常の税率が適用されます。つまり、将来的な長期的な固定資産税負担は減らすことができない点がデメリットです。
適用条件の厳格化: この軽減措置は、120㎡以下の居住部分に限られるため、広い住宅を検討している場合や二世帯住宅の場合、軽減の対象外となる部分が出てくる可能性があります。
耐震改修や省エネ改修による減税
「耐震改修」や「省エネ改修」を行うと固定資産税の減税が適用される制度があります。これにより、古い住宅に住み続けるための負担が軽減されるとともに、地震や環境への備えができることが魅力です。
耐震改修による減税
耐震改修を行うことで、一定期間固定資産税の減税が受けられます。特に、昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物が対象です。条件を満たす耐震改修を行うと、住宅部分の固定資産税が最大50%減額され、1年間にわたって適用されます。たとえば、通常の固定資産税が年間10万円の物件であれば、5万円の減税効果が期待できます。
メリット
災害時のリスクを軽減できる点です。耐震性の強化により、地震による倒壊や損壊を防ぎ、家族や財産を守ることができます。また、減税によって初期投資の一部を回収できる点も利点です。
デメリット
耐震改修の工事費が高額になるケースがあることです。一般的な耐震改修費用は100万円以上となるため、減税効果が工事費に見合わない場合も考えられます。
省エネ改修による減税

省エネ改修(断熱性能向上やエコ機器の導入など)も、固定資産税の減額対象になります。具体的には、改修費が50万円以上であること、断熱窓や太陽光パネル、エコキュートなどを導入することが条件です。これにより、住宅部分の固定資産税が最大3分の1減額され、同じく1年間適用されます。
メリット
光熱費の節約効果が長期間にわたり得られる点です。断熱改修により冷暖房効率が高まり、光熱費の削減が期待できます。また、環境にも優しい生活が実現します。
デメリット
省エネ設備や断熱材の設置費用が高くなることです。例えば、断熱窓の交換は数十万円かかることが多いため、初期費用の負担が大きくなる可能性があります。
節税効果の実際と注意点
このような改修による減税は、固定資産税の一時的な減額を可能にし、経済的負担を軽減する一方で、改修工事が対象基準を満たす必要があるため、計画的に行うことが重要です。また、減税適用を受けるためには、各市区町村への申請が必要です。申請には、工事の契約書や領収書などの提出が求められるため、書類管理も注意が必要です。
住宅ローン減税と固定資産税
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して新築やリフォームを行った際、所得税の控除が受けられる制度です。これは毎年の所得税額から住宅ローン残高の一定割合が控除され、長期的に負担を軽減できるものです。また、所得税から控除しきれなかった分については住民税からも一部控除され、実質的に固定資産税の負担を抑える効果が期待できます。
住宅ローン減税の基本ルール
2024年度現在、住宅ローン減税の控除率は1%で、最大で年40万円まで控除が可能です。この控除額は10年間適用され、新築や省エネ住宅の場合、一定の要件を満たすと13年まで延長されます。控除額をまとめた表を以下に示します。
| 住宅タイプ | 控除期間 | 控除率 | 年間控除上限額 |
| 一般住宅 | 10年 | 1% | 40万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 13年 | 1% | 40万円 |
| 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 13年 | 1% | 50万円 |
※控除期間の延長には、購入住宅が省エネ性能などの基準を満たしている必要があります。
メリット
1. 所得税・住民税の控除による実質負担軽減
住宅ローン減税は所得税だけでなく、住民税の控除にも反映されます。例えば、所得税の控除限度額を超えた分は、最大で年間13.65万円まで住民税からも控除されるため、トータルの負担が軽減されます。これにより、固定資産税の支払いも経済的な負担を感じにくくなります。
2. 節税効果とキャッシュフローの改善
特に10年~13年間の控除期間中、毎年返済額が一定の収入から控除されるため、手元資金に余裕が生まれます。節税のメリットを受けながら、資産形成がしやすくなるという利点があります。
1. 控除の受けられる期間が限られている
住宅ローン減税は最長で13年までしか適用されません。そのため、13年以降は控除の恩恵がなくなり、固定資産税や住民税の負担が増えることを考慮する必要があります。
2. 条件を満たす必要がある
住宅ローン減税には、「床面積が50㎡以上」「住宅の取得から入居までの期間」「耐震基準を満たしている」などの条件があります。また、ローンの年収上限(2024年度は2000万円)も設定されているため、これを超えると適用外になる点には注意が必要です。
実際の節税例
例えば、4000万円のローンを組み、年間返済額が40万円である場合、控除率1%のもとで年間40万円の所得税控除が可能です。もし控除額が所得税額を上回った場合、その残額は住民税から控除されるため、トータルで負担が軽減されます。
住宅ローン減税により実際の手元キャッシュフローが増え、生活資金に余裕が生まれるのも大きなメリットです。
住宅ローン減税は、所得税と住民税の負担を抑えながら、実質的に固定資産税の負担を軽減できる優れた制度です。制度を活用する際は、対象要件や控除可能期間、年収制限をしっかり把握し、計画的に利用することが重要です。特に新築住宅や省エネ住宅ではさらに延長されるメリットがあるため、長期的に資産形成を考えている人には有効な手段といえるでしょう。
自治体ごとの減税制度

自治体ごとの減税制度は、各地域で定められた固定資産税の軽減措置や住宅取得支援を通じて、住民が負担する税金を減らすための重要な制度です。地域により制度が異なり、対象となる住宅や改修の種類、申請条件、減税額も多様です。新築住宅を検討している方や税負担を軽減したい方には、居住地域で提供されている減税制度を確認することが節税に役立ちます。
| 減税制度 | 対象 | 減税内容 | 条件例 |
| 新築住宅に対する固定資産税減免 | 一般住宅 | 最長3年間の固定資産税半減 | 床面積50㎡以上、新築から一定期間内の申請 |
| 省エネ住宅に対する補助金 | 省エネ基準を満たす住宅 | 補助金支給、または固定資産税の軽減 | 地域ごとに基準や補助金額が異なる |
| 空き家再生支援 | リフォーム済みの空き家 | 固定資産税軽減や補助金支給 | 空き家の状態や改修内容に基づく要件 |
このように、自治体が提供する減税制度は多岐にわたります。特に、新築や省エネ対応の住宅は対象となることが多いため、購入時には自治体の支援内容を確認しておくことが大切です。
自治体の減税制度の例
東京都の新築住宅減税制度
東京都では新築住宅に対し、固定資産税の軽減が提供されており、住宅が50㎡以上であれば、最長3年間にわたり税額が半減されます。例えば、固定資産税が年間20万円であれば、3年間で最大30万円の軽減効果が見込まれます。住宅購入の際は新築に対する優遇が強い地域かを確認し、制度活用を検討しましょう。
省エネ・エコ住宅支援制度
神奈川県では、断熱性や省エネ設備を備えた住宅への補助金制度があり、対象住宅は固定資産税の減税も受けられることが多いです。例えば、省エネ基準を満たす新築住宅に対し、5年間の固定資産税減免が適用される場合もあります。また、自治体によっては地域のエコ推進方針に応じた補助があるため、省エネ対応の住宅は多様な減税の恩恵が期待できます。
メリット
1. 地域の税負担軽減が期待できる
自治体の減税制度を利用することで、固定資産税の負担を軽減するだけでなく、地域の補助金や助成金の活用も可能です。特に新築や省エネ対応の住宅では多くの自治体で優遇が設けられており、実質的な税負担が大幅に下がるため、家計負担の軽減に寄与します。
2. 長期的な資産価値向上
省エネ住宅や耐震改修が行われた住宅には、補助金が支給されるケースが多く、住居の資産価値が向上するため売却時にも有利です。また、自治体の補助制度は物件のメンテナンス費用の軽減にも役立つため、長期的な資産維持の観点でもメリットがあります。
デメリットと注意点
1. 制度が地域によって異なる
自治体の減税制度は地域によって内容が大きく異なるため、事前に調べて申請手続きを確認する必要があります。全国共通ではないため、地域によっては期待するほどの節税効果が得られない場合もあります。
2. 要件を満たすための手続きが必要
多くの減税制度には申請期限や要件があり、手続きが煩雑です。特に新築後の一定期間内に申請が必要なケースが多く、タイミングを逃すと減税の恩恵を受けられないことがあるため、注意が必要です。
まとめ
自治体ごとの減税制度を利用することで、固定資産税の軽減や住宅購入後の負担減が期待できます。制度は地域ごとに異なるため、購入前に自治体の窓口やウェブサイトで最新情報を確認することが推奨されます。また、省エネ対応や空き家のリフォームなど、自治体が積極的に支援する分野に対しても目を向けることで、節税の幅を広げることが可能です。

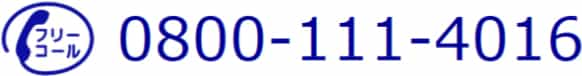







を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)



