家を建て替える際に失敗しないためのコツ!手順・準備・費用・期間など

家を建て替えて住み替える、使っていない古家を取り壊し新築するなど建て替えを検討している人は多いことでしょう。しかし、建て替えには多くの手続きや準備などがあり、費用や入居までの期間を把握しなければいけないなど知っておくべきことが多くあります。
本記事では、家の建て替えについて、建て替えの手順・準備・費用・期間などについて解説します。記事を最後まで読み進めていただければ、家の建て替えについて必要な基礎知識が得られ、建て替えがスムーズに進むことでしょう。
家の建て替えの手順
家を建て替えるときには、多くの手順を踏むことになります。具体的な手順は、次のとおりです。
- 建て替えの準備をする
- 建築会社を探す
- 建築会社と設計プランの相談
- 建築会社と工事請負契約締結
- 住宅ローンの申し込み
- 解体業者を決定し手配
- 仮住まいへの入居
- 解体工事開始
- 地盤調査・地盤改良
- 新築工事開始
- 引き渡し
上記のように家を建て替えるときには、多くの手順があります。ここからは、手順の中で特に気を付けなければいけないこと、注意しなければいけないポイントに絞って解説していきます。
建て替え前にしておくべき準備
家の建て替えをするときには、建築会社を探すよりも前にやっておかなければいけない準備があります。建て替えができるのかどうかを確認したり、建て替えの今後の方針を決めたりしなければいけません。本章では、どのようなことを準備すればよいのかについて解説します。
再建築不可物件でないことを確認する
土地の中には、建物を壊してしまうと再建築できなくなる土地があります。そのため、建て替える予定の土地が再建築不可物件でないことを確認しましょう。
再建築不可物件である可能性がある土地は、次のとおりです。
- 市街化調整区域に該当し地目が宅地になっていない
- 土地に接道している道路が4m以上であり道路の間口が2m未満
- 道路に接していない土地
このような条件に該当する土地に建て替えを検討しているときには、建て替えできないケースがあるため注意しなければいけません。条件に引っかかるかもしれない土地に建て替えるときには、建て替えができるかどうか必ず建築会社の担当者に確認しましょう。
なお、一見道路に接しているように見えても、接している道路が建築基準法上の道路でない場合も再建築不可物件になる可能性があります。建築基準法上の道路かどうかは建築会社が確認してくれます。
どのような家にするのか家族と話し合っておく
新しく建築する家の内装や間取り、大きさなどあらかじめ家族と話し合っておきましょう。
家は同居する人全員に使い勝手のよいものにしなければいけません。自分だけ使い勝手のよい家を建築してしまうと、家族のストレスにつながってしまうため気を付けましょう。
予算を決めておく
建て替えをするときには、建築費用や解体費用、諸費用など多額の費用がかかります。もし予算を決めずに進めてしまうと、予算が足りなくなる、予算が膨れ上がって生活が苦しくなるなどのリスクが発生します。
このようなことにならないよう、おおよその予算を建て替えまでに家族と話し合って決めておきましょう。もし予算がなかなか決められないというときには、住まいの無料相談などでファイナンシャルプランナーに確認するとよいでしょう。
家を建て替えるときに必要な費用目安
建て替えをするときには多くの費用がかかるため、いつ・どのような・どれくらいの費用がかかるかを知っておかなければいけません。本章では、家を建て替えるときに必要な費用をケースごとに分けて解説します。
建物を解体する費用の目安
建物を解体するときには解体費用がかかります。
解体費用は壊す家の構造により費用が変動します。構造による費用変動目安は次のとおりです。
- 木造:坪あたり4万円~5万円
- 軽量鉄骨造:坪あたり6万円~7万円
- 鉄筋コンクリート造:坪あたり6万円~8万円
たとえば、40坪の木造住宅を解体するのであれば
40坪 × 4万円/坪~5万円/坪 = 160万円~200万円
つまり、解体費用は160万円~200万円が目安になります。ただし、解体費用は解体現場に重機が入るのか、解体中に警備員がいる現場なのかなど費用変動する項目がいくつもあります。そのため、正確な解体費用を知りたい人は、解体業者から解体見積もりを取得しましょう。
建物を新築するときの費用目安
建物を新築するときには、次のような費用がかかります。
- 本体工事費用
- 付帯工事費用
- 建築に関わる諸費用
上記の費用目安を計算する場合は、本体工事費用金額を基にして算出します。算出方法は次のとおりです。
(建物の坪単価 × 建築延面積)÷ 75% = 建物を新築するときの費用目安
たとえば、建物坪単価90万円、建物延面積40坪の家を新築する場合
(90万円 × 40坪)÷ 75% = 4,800万円
このケースの場合、4,800万円が建物を新築するときの費用目安となります。
諸費用の目安
家を建築するときには、印紙税や保険料、各種手数料などの諸費用がかかります。
家を建築するときの諸費用は、建物本体工事価格の6%前後とされています。
たとえば、建物本体工事価格が4,000万円のときの諸費用目安は
4,000万円 × 6% = 240万円
このケースの場合、諸費用の目安は240万円となります。
家を建て替えるときの期間目安

家を建て替えるときの期間は、おおよそ1年~1年半かかると考えてきましょう。
建て替えの準備から新築工事着工までおおよそ6ヶ月~8ヶ月、新築工事着工から入居まで6ヶ月~8ヶ月かかります。
ただし、設計などの打ち合わせが少なく済んだり、建築工事に時間がかからない工事方法だったりすると期間が短縮されます。どのくらい時期が変わるのかは、依頼する建築会社の作成した工程表を確認されてもらうとよいでしょう。
なお、仮住まい先は建物着工2ヶ月前くらいから始めるとよいでしょう。仮住まいは早く探し始めすぎても入居日が決められないですし、探すのが遅すぎるとよい仮住まい先がみつからず生活にストレスがかかってしまう可能性もあります。
建て替え費用を削減するためのポイント
建て替えするときには多額の費用がかかります。しかし、費用削減のポイントを抑えれば費用削減できるケースもあります。本章では、建て替え費用を削減するためのポイントについて解説します。
複数の建築会社に建築見積もりを取得
新築する家を建てる建築会社が決まっていないときには、複数の建築会社から建築見積もりを取得しましょう。
複数の建築会社より建築見積もりを取得することで、建築費用相場が理解できます。相場が分かってこれば、どの項目がどのくらい高いのか安いのかも分かり、建築会社への値段交渉がしやすくなります。
見積もりを比較するためには、3社~4社から建築見積もりを取得するとよいでしょう。
また、建築会社によっては、他の会社で見積もりを取得していることが分かると「建物請負契約をしてくれるなら値引きします。」というような交渉を建築会社から提案してくるケースも出てきます。
シンプルな形の家を建築する
シンプルな形の家を建築すると建物の建築費用を抑えることが可能です。
建築費用は基礎の面積や柱の本数、壁の枚数などによって変動します。建物をいびつな形にすると、基礎の面積や柱の本数などが増えてしまい費用も上がってしまいます。しかし、四角の箱形の家を建築すれば、基礎の面積などが抑えられて建築費用も抑えることが可能です。
給付金や補助金などを利用する
建築する建物や設置する設備によっては、給付金や補助金などが出るため、受給できる要件を満たしているときには必ず利用しましょう。
補助金が出る制度としては「こどもみらい住宅支援事業」などがあります。
こどもみらい住宅支援事業とは、子育て世帯や若者夫婦世帯が省エネ高性能住宅を建築・購入などした場合、最大で100万円の補助を受けられる制度です。
このような補助を受けられる制度はいくつかありますが、補助条件や制度の利用期限などがあるため、利用できる制度については建築会社の担当者に確認しておきましょう。
建て替えをするときには住宅ローンに注意
新築する住宅の費用を住宅ローンで支払う場合、まだ現在の住まいに住宅ローンが残っているときには注意が必要です。
現在の住まいに住宅ローンが残っていないときには、新築する住宅建築時に通常通りの住宅ローンで対応可能です。しかし、現在の住まいに住宅ローンが残っているときには、通常の住宅ローンは利用できません。
現在の住まいに住宅ローンが残っているときには「住み替えローン(建て替えローンと呼ぶケースもある)」を利用します。住み替えローンは、現在の住宅ローンの残高を新築住宅のローンに上乗せできるローンです。
住み替えローンは建て替えするときには便利なローンですが、借入額が大きくなることと、審査が厳しくなることには注意しましょう。
まとめ
家を建て替えるときには、多くの手順があり入居までにおおよそ1年~1年半かかります。そして、家を建て替えるときには、建物建築費用や解体費用など高額な費用がかかります。そのため、建て替えをする前からしっかりと準備をして、建て替えに望まなければいけません。
また、建て替えをするときの費用は、複数の建築会社から見積もりを取得したり、補助金などの補助制度を利用したりすれば抑えられます。
事前準備をしっかりと行い、費用を抑えれば建て替えがうまく進み、満足いく新居での生活が送れることでしょう。

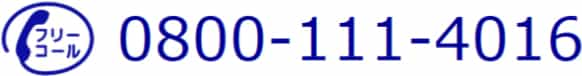









を分かりやすく解説-1-180x180.jpg)

